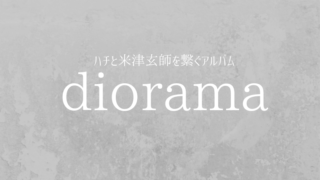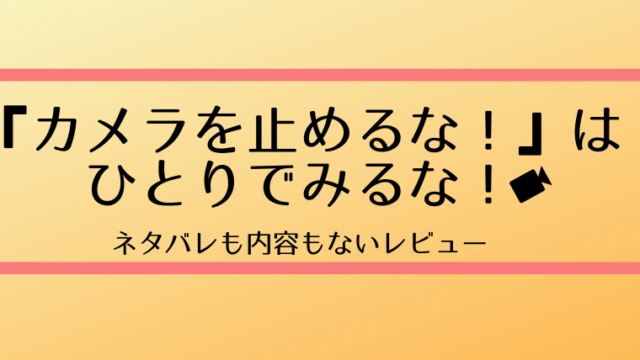米津玄師の【YANKEE】という暴力じみたアルバム
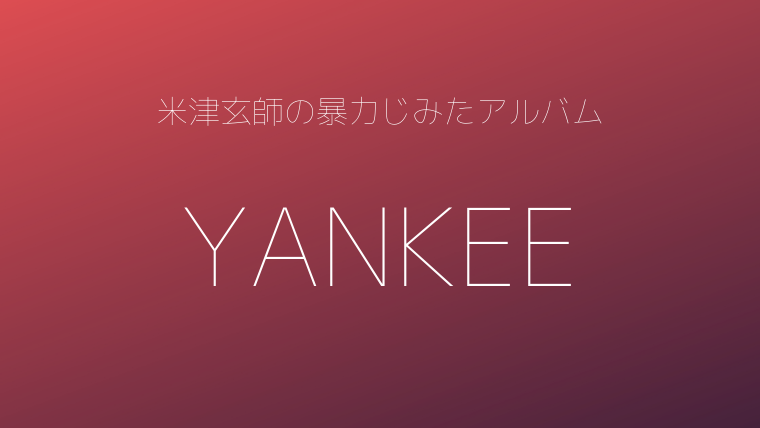
YANKEEという雪崩。
米津玄師、もう説明不要に大きくなった彼。ここでは彼の2ndアルバム【YANKEE】の魅力を書いていきたい。
(2014年のメモより抜粋記事)
もくじ
もはや全曲シングル
初動殴り込み
このアルバム、開幕から殴り込みをしてくる。
一曲目から、『リビングデッド・ユース』。二曲目に『MAD HEAD LOVE』、次に『WOODEN DOLL』、そして4曲目『アイネクライネ』。ここまで全てMVありのリードトラック。ぶっ壊れてる。
一般的な音楽アルバムであれば、リードトラックは散っている事が多く、普通固めない。なのに【YANKEE】では、MVのある曲の殆どを最初にぶち込んだ。よほど自信がないとこんな事出来ない。とんでもない。
後半も殴り込み
4曲目の『メランコリーキッチン』が終わり、『サンタマリア』で少しアルバムのテンポが落ちる。「そろそろ落ち着く」そう思った。ところがどっこい、米津玄師は殴るのをやめない。
次に始まるのは「花に嵐」。ゴリゴリのストレートロック。(ちなみに、この曲米津玄師にしてはシンプルに聴こえるが、ギターは3本で、複雑に噛み合っていて、特にリードギターは結構な手数だったりする)
『サンタマリア』はこのアルバムの第一のセーブポイントだった。あそこでちゃんとセーブしなかったらパーティはたちまち全滅していた。
落ち着いたと思ったらこの様だ。休む間もなく、高・中BPMで殴り込んでくる。ロック『花に嵐』、文学『海と山椒魚』、どんちゃかソング『しとど晴天大迷惑』。この三曲が雪崩込んで来る。耳が休むことを許されない。許して。
この殴り込みは最初の4曲で食らったぞ? でも休まない米津玄師。そこにさらにマウントとって、まだ畳み掛けてくるのが米津玄師。鬼畜か。「YANKEE」だよまさに。アメリカの移民の意味じゃないほうのヤンキーだよこれ。
第二のセーブポイントである「眼福」が終わってからまた勢いを戻し、『ホラ吹き猫野郎』に『TOXIC BOY』で雪崩込み。
「またアルバム始まった」 と思う。米津玄師やはり許してくれない。
聴く文学
「diorama」時代の米津玄師を歌詞を「物語」とするなら、「YANKEE」の歌詞は「文学」だ。このアルバムの米津玄師はもはや”聴く文学”だと思う。どれを聴いたって、一聴で言葉を理解させるつもりがない。
普段読書をよくするそれなりに語彙のある人間でも、ぱっと聴いただけでは分からない。それほど歌詞が美しい。
「この言葉・表現歌詞に使っちゃうの?」となる。万人受けする曲とは桁違いの語彙と表現が詰まっている。なのに万人受けする。そこが凄まじい。
「海と山椒魚」が顕著に聴く文学をしていると思う。歌詞とメロディが天元突破して美しい。どの曲もメロディが綺麗だったり面白かったりするけど、「海と山椒魚」は「もうこれ国有財産にしてくれ」と思うレベルでメロディ・歌詞・伴奏が素晴らしい。この曲を聴いた時は、「音楽って素晴らしい」と改めて思った。名曲にも程がある。
全体の歌詞も本当に素晴らしいのだけど、特にCメロのこの部分。
青く澄んでは日照りの中 遠く遠くに燈が灯る
それがなんだかあなたみたいで 心あるまま縷縷語る
この部分のメロディと語感のよさ。なぜここまで心地良いのか考えてみると、この部分「7・5(6)・7・5」「7・7・7・5」というリズムになっていて、短歌の形式で自由律定形をとっていると気がついた。なので、このフレーズは日本人に特に馴染みあるものになっているのかもしれない。
※試聴部分はCメロではないけど一応
音楽性の高さ
歌詞の分かりにくさなんてぶっとぶくらいに中毒性があるのがこのアルバム。前アルバム『diorama』ではボカロの名残か、打ち込みサウンドが多かったが、『YANKEE』では全体的にバンドサウンドになっている。『diorama』の宅録とは違い、スタジオレコーディングもしている。
バンドサウンドに加えて、変な音源(褒め言葉)が鳴っていて、それがいい味を出している。ギター、ベース、ドラムもめちゃくちゃ複雑な噛み合い方をしてるんだけど、変な音源と中毒性がそれをさらに手助けする。質が高すぎる。何度も聴いてしまう。(どのパートもかなり複雑に絡み合ってて、特にドラムがめちゃくちゃ難しい)
歌詞が、比較的(あくまで)わかりやすいのは、『MAD HEAD LOVE』や『ドーナツホール』だが、それでもポップソングとしては比類ないわかりにくさをもっている。その音楽性の高さから、言葉が理解できなくても、自分含め、あらゆる人間の心を鷲掴みにした。
結びに
このアルバムはとんでもない。米津玄師の暴力。全曲シングルカットしてもいいアルバムだと思うくらい、各曲のクオリティが高い。「diorama」はアルバムを通して聴くのが一番だと思うけど、「YANKEE」は単品で抜いても大丈夫。アルバム通してでも、もちろんハイクオリティ。
こんなに密度が高いアルバムは本当に中々ないので、もし聴いたことが無ければ聴いて欲しい。これを米津玄師の一番の名盤との声も多く、2014年にiTunesベストにも選ばれている実績もある。
こぞって音楽関係の人間が、彼を「10年に1人の才能」だと表現している。この音楽性の高さは誰が聴いても、そう思わざるを得ないと思う。圧倒的だった。彼が出てきてから、もう数年経つけど、彼を超える才能をまだ見てない。
彼は才能を持った上で、突き詰める努力者である。自分が見つけてないだけかもしれないので、米津玄師を超えると思うアーティストがいれば是非教えてほしいです。音楽に超える超えないの優劣はないですが。
それではまた。
<文・編集 = hitoto(@tonariniwa)